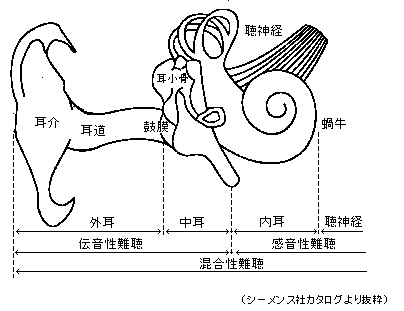| 部 位 | 音の伝わり方 |
| 耳介(じかい) | 音(空気の振動)を集める。 |
| 外耳道(がいじどう) | 音を鼓膜に導く。 |
| 鼓膜(こまく) | 音を受けて薄い膜が振動する。 |
| 耳小骨(じしょうこつ) | ツチ、キヌタ、アブミの3つの骨が鼓膜の振動を内耳に伝える。 |
| 蝸牛(かぎゅう) | 内部がリンパ液で満たされていて、音の振動を電気信号に変える。 |
| 聴神経(ちょうしんけい) | 音を電気信号によって脳に伝える。 |
| 脳:聴覚中枢(のう:ちょうかくちゅうすう) | 音や言葉を認識する。 |
聴覚障害の原因と種類
◆障害者の定義
障害者基本法では、「この法律において”障害者”とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」としています。国際障害者年行動計画(1980年)には、「障害者は、社会の異なったニーズをもつ特別の集団と考えられるべきではなく、通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難を持つ普通の市民と考えられるべきなのである」とあります。
障害者と健常者は同じ権利を有する住民であり、対等な立場で社会参加する一人として障害者を支援する時代へと、国の考え方も大きく変化してきました。
◆聴覚障害の原因
聴覚障害になった時期により、先天的、後天的に分類されます。
| 先天的 | 聴覚組織の奇形や、妊娠中のウイルス感染(特に風疹)などで聴覚系統がおかされた場合 |
| 後天的 | 突発性疾患、薬の副作用、頭部外傷、騒音、高齢化などによって聴覚組織に損傷を受けた場合 |
◆聴覚障害の種類
聴覚障害になった部位により、伝音性難聴、感音性難聴、混合性難聴に分類されます。
聴覚障害になった部位により、伝音性難聴、感音性難聴、混合性難聴に分類されます。
| 伝音性難聴 | 外耳、中耳の障害による難聴 音が伝わりにくくなっただけなので、補聴器などで音を大きくすれば、比較的よく聞こえるようになります。 治療によって症状が改善される場合もあります。 |
| 感音性難聴 | 内耳、聴神経、脳の障害による難聴(老人性難聴も感音性難聴の一種です。) 音が歪んだり響いたりしていて、言葉の明瞭度が悪い。補聴器などで音を大きくして伝えるだけではうまく聞こえません。補聴器の音質や音の出し方を細かく調整する必要があります。 |
| 混合性難聴 | 伝音性難聴と感音性難聴の両方の原因をもつ難聴 |
聞こえの不自由な人を聴覚障害者と言いますが、聴覚障害の原因や種類、聞こえの程度が様々なため、聴覚障害者を分類し定義することは非常に難しい。聴覚障害者は、 「中途失聴者」、「難聴者」、「ろう(あ)者」に分かれますが、その人がどれに当たるかは、その人自身がどう思っているかというアイデンティティの問題でもあるのです。
「中途失聴者」と「難聴者」の両方を含む広い意味で「難聴者」という場合があります。
| 中途失聴者 | 音声言語を獲得した後に聞こえなくなった人で、まったく聞こえない中途失聴者でも、ほとんどの人は話すことができます。 |
| 難聴者 | 聞こえにくいけれど、まだ聴力が残っている人です。補聴器を使って会話できる人から、わずかな音しか入らない難聴者まで様々です。 |
| ろう(あ)者 | 音声言語を習得する前に失聴した人で、そのため、手話を第一言語としている人がほとんどです。 |